
あなたの便秘のお悩みを解消します。
『下剤連用の結末は…』
現役消化器内科医師かつ腸内フローラデザイナー(自称)のわたしが、
便秘でお悩みの方に届けたい、切実な想い。
どうか3-5分ほどお付き合いください。
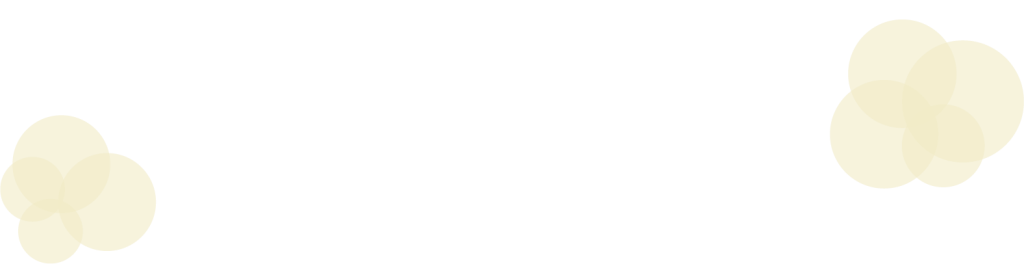
うんちをスッキリ出さないと気が済まない。
便秘でお困りのあなた、
刺激性下剤を連用してませんか?

本題へ入る前に
私は地方のクリニックに勤めている平凡な消化器内科医です。
おなかの診療を専門として日々診療を行っておりますが、中でも便通異常には力を入れており、患者様の未来を見据えた診療をしております。
一方で、
「腸内フローラから、豊かな人生をデザインする。」をコンセプトとした、『フローラデザインプロジェクト』を立ち上げるなど、腸内フローラと日々向き合うことを日課としており、
勝手に自らを『フローラデザイナー』と名乗っております。
今回は、そんな背景をもつわたしが、
日々の便秘診療の中で感じていること、みなさんに知っておいて欲しいことをお話していきます。
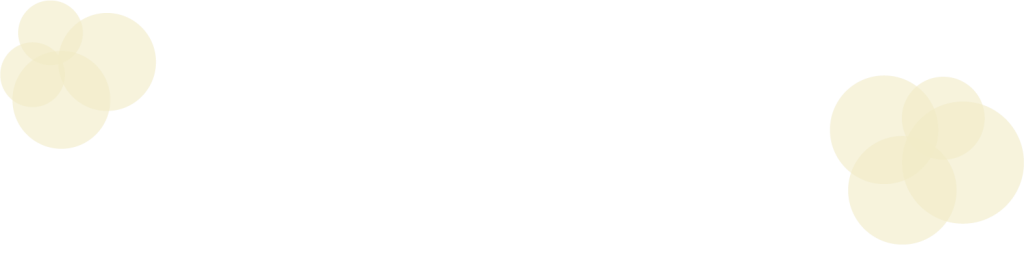
本題へ
うちのクリニックには便秘でお困りの方が毎日たくさん受診されます。
しかし、それは氷山の一角に過ぎません。
医療機関には来院されず、自己流で奮闘されている方もたくさんいらっしゃいますね。
ということは、全国には一体、どれだけ
たくさんの便秘でお困りの方がいらっしゃることでしょうか。
お読みいただいているあなたもそのおひとりかもしれませんが、
残念ながら便秘でお困りの方の多くは、あまり好ましくない解決策をとっていることが多いです。
便秘でお悩みのあなたは、
普段どういった対策をされてますか?
食事、運動、マッサージ、専門家に相談、病院やクリニック受診、
などなど
・色々やったけどダメだったから市販の下剤を使っている。
・病院に通い始めた時は良かったけど、だんだんと調子が悪くなってきた。
そんな方も多いのではないでしょうか。
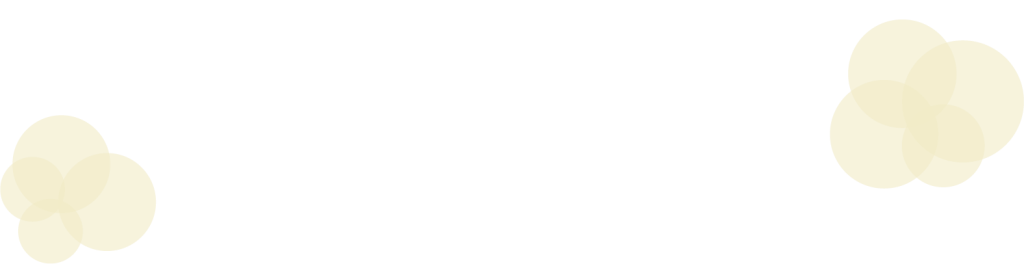
正しくやれば必ず道は開けますが、間違えば泥沼にハマります。そうならないために、これから正しい知識をお伝えしますね。

長期で便秘でお悩みの方のは多くいらっしゃいますが、そのほとんどが刺激性下剤というものを長期連用されているんです。
タイトルにも「刺激性下剤」ってありましたが、一体「刺激性下剤」とは何でしょうか?
「刺激性下剤」は、ドラッグストアでも病院でも手に入る下剤の一つで、
文字通り「腸を刺激する」ことにより排便を促し、便秘を解消するものです。
しかし、「刺激性下剤」はあなたにとって味方にもなればに敵にもなるお薬なんです。
それはなぜでしょうか。
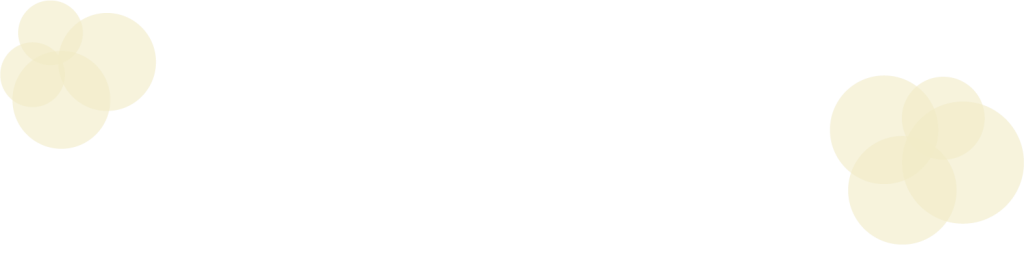
その前に、そもそもどんなものを「刺激性下剤」というのかの具体例を挙げますね。

「刺激性下剤」具体例
例えば、有名どころでは、コー●ックファーストやス●ーラックSとか、武●の漢方胃腸薬、●り●りスリムなどの健康茶の一部、など。その他たくさんの市販薬があります。それから処方箋の必要な医薬品ではプルゼニド(センノシド)やピコスルファート(ラキソベロン)などが有名です。
使用された方も多いのではないでしょうか?
使用されたことがない方も、ドラッグストアに行った際には便秘コーナーをご覧ください。簡単に見つかると思います。
もちろん「刺激性下剤」ではない下剤もありますよ。
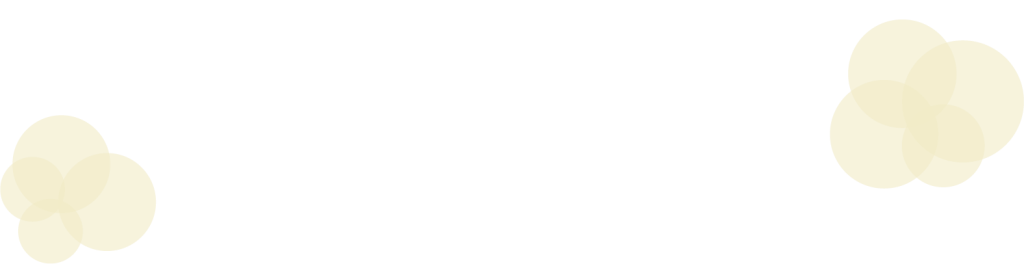
なぜ、「刺激性下剤」は味方にも敵にもなるのか。
解説致します。
まず大腸には神経があるんですが、「刺激性下剤」は大腸の神経を刺激することで大腸を動かすんです。
具体的には、大腸粘膜の下のアウエルバッハ神経叢というものを刺激して、蠕動運動(腸の運動)を促すんですね。
しっかりと腸を動かしてくれるので、何日も溜めっていたものがごっそり出て、スッキリします。とてもありがたい存在です。

でも、ここからがポイント!
「ごっそり、スッキリ」
これが癖になってしまいます。
つまり習慣性や依存性があるということ。
なんとなく毎日は使わない方が良いのはわかっているけどやめられない。
タバコに近いかも知れません。
「刺激性下剤」はどうしても出ない時に時々使うのは有効!!
ですが、毎日使いは避けましょう。
長期連用すると、だんだん効きが悪くなるからです。
なぜでしょうか。
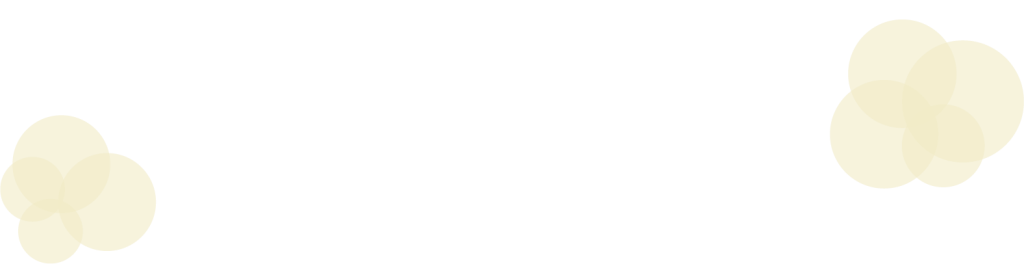
「大腸と刺激性下剤」=「馬と鞭」
「大腸と刺激性下剤」を「馬と鞭」に例えて考えてみましょう。
(大腸が馬🐎、刺激性下剤が鞭)
「刺激性下剤」は腸の神経を刺激します。

腸にビシっと鞭を打つようなものですから、最初はちょっとした刺激でも腸はがんばりますが、休みなくビシビシと繰り返していくと腸はだんだん疲弊します。そして軽く鞭を打つだけでは動かなくなり、強くビシバシと引っ叩かれてやっと動くという状態に。
腸はヘトヘト、腸の神経はズタボロ
そうすると
👇
最初は月1の内服だったのが、
月1→週1→週3→毎日
1錠→2錠→6錠→10錠
と、こんな感じに回数も錠数も増えていくわけです。
そうしてはじめて医療機関に受診される方も多くいらっしゃいます。
ここまで来ると、かなり大変
(ここまで来ている方は、専門の医療機関にご相談を)
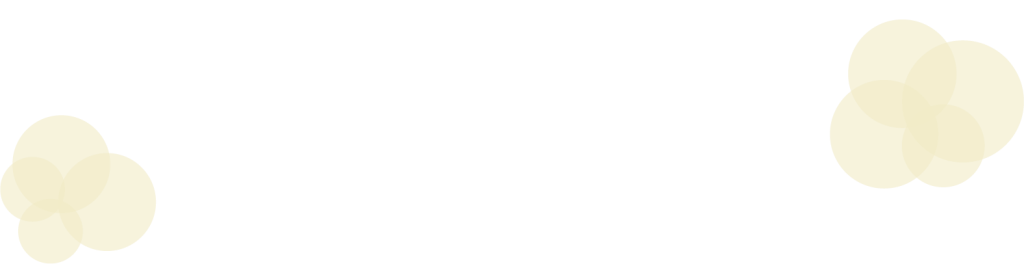
どうしてこういうことが現実になってしまうのかを深掘りしましょう。
これらのお薬は使い方さえ間違わなければとても良いお薬ですが、使い方を間違えれば毒になります。
連用はダメ✖️、ということです。

でも、使い方に毎日服用出来るって書いてあるじゃないか、という声が聞こえてきそうです。
ですよね😥
服用方法のところに1日1回1〜4錠(コー●ックファースト)とか書いてあれば毎日服用してしまいますよね😵どうして未だにこういう表記なのか。本当にこれは罪深いと思います😔
医療機関から処方されるものも一日一回って書いてある〜、という声も聞こえてきそうです。
これはいくらか仕方ないところもありまして、少し説明させてもらいます。
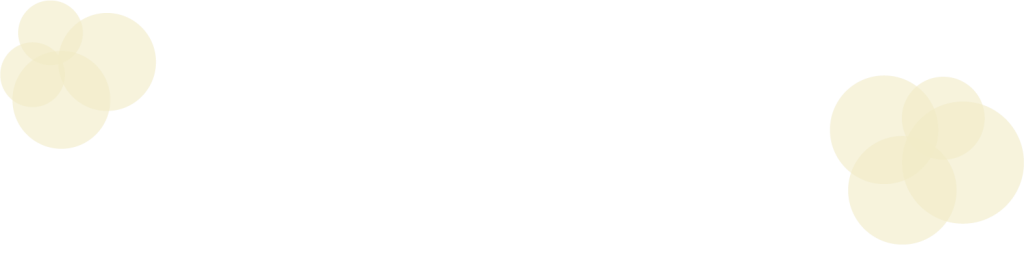
医薬品には審査がありますが、過去に「*服用方法:一日一回」でその審査を通しており、今更製薬会社としては一日一回という服用方法の記載を変えられない、ということはあるのかもしれません。(そのあたりに精通している訳ではないのであくまで推測です。審査を通すには治験と言って大規模な臨床試験が必要。)
あとは、「どうして刺激性下剤が市販されているのか」という疑問もあると思います。
それはそれにより救われている方がいるからでしょう。

便秘でお困りの方はたくさんいるのに、「便秘ごときで医者にかかるのはどうか」と思われてしまう方も多く(実際はそんなことありません。便秘でお悩みの方に優しい医療機関も現実はたくさんあります)、そんな方にとっては市販薬の下剤というものは大変重宝されるものであり、社会的価値も高いのです。
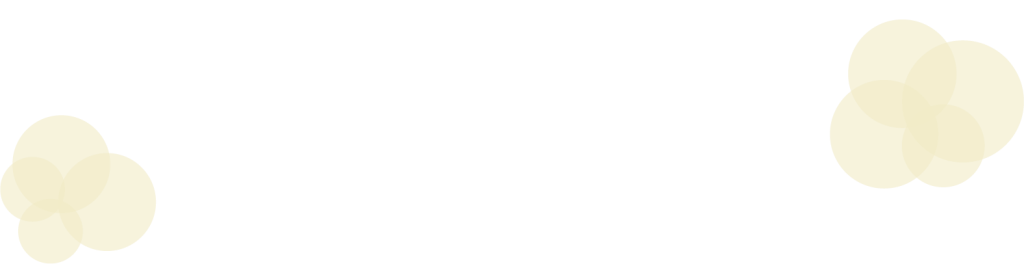
また、「病院では刺激性下剤をどうしてずっと処方されているのか。」というお声も聴こえてきそうです。
昔は便秘薬もそう多くはなく、医師が処方する武器が非常に少なかった。患者さんも通常は現状が良ければ良いと思っているので、増量以外の変化はあまり望まない。
それで昔の処方をそのまま続けてしまっている、というパターンはよくあります。
実際、刺激性下剤をやめてしまうとまったく出なくなってしまうことも多いので、患者さんにとっては「欠かせない大切なお薬」、医者にとっては「変えるに変えられないお薬」ということにもなり得ます。

下剤は「刺激性下剤」だけではないと医師はわかってはいるのですが、上記のような理由で一日一回の服用方法で継続処方されているケースはあるでしょう。
処方や服用方法の変更には
「医師の正しい知識と根気」、
「患者さんの正しい理解と根気」
がいるのです。
注)連用はよろしくないですが、頓用で使用すれば(週に1-2回以下)問題は少なく、有効なことが多いので、頓用使用は許容されます。
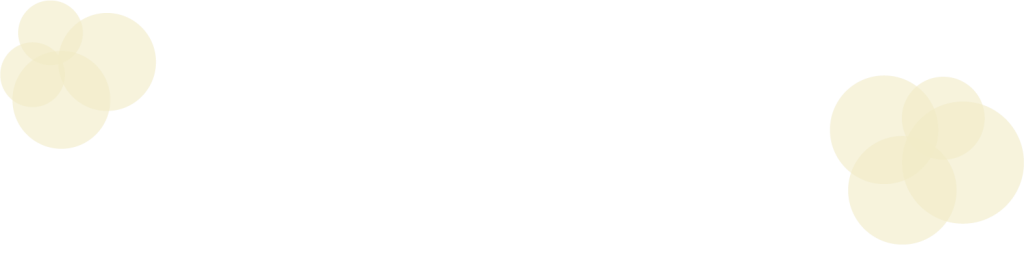
刺激性下剤の連用をしている場合はどうしたらよいのか。
大丈夫です。
医療は常に進歩していきますが、便秘薬も進歩し、最近はいくつかの新薬が続け様に出てきております。
これらの武器を駆使すれば、刺激性下剤からの脱却は可能です。
いま泥沼にハマってしまっている方は、是非便秘を得意とする医療機関に受診して相談をされてください。
刺激性下剤は急にはやめれせん。
いきなり中止すると急に鞭が無くなるわけですから、馬は動きません。とんでもない便秘になります。
焦る必要はありません。
ゆっくり解決していけば良いです。
病院で相談して、代替となる薬を処方してもらい、徐々に減量しましょう。
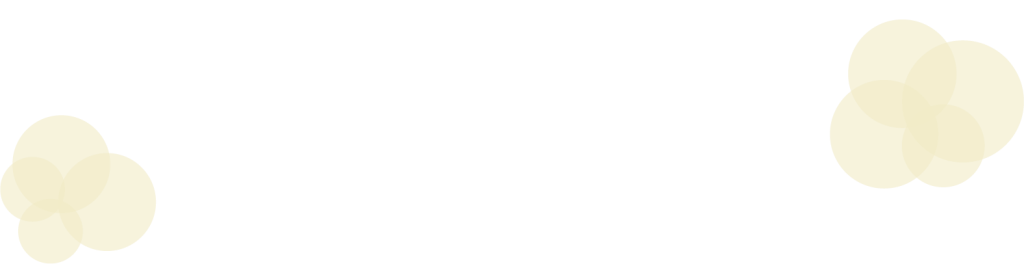
とにかく焦りは禁物です。
週1〜2回くらいの使用は許容されますので、全く無しにする必要はありません。
ただし、使っているとどんどん使いたくなる依存性がありますから、可能な限り控え、0を目指しましょう。

それから出来ればなんらかの原因疾患が無いかどうかを相談してください。
その際は、大腸癌などの病気が無いかも含めて相談出来る医療機関をお勧め致します。
また、大腸癌だけではなく、糖尿病や甲状腺機能低下症、パーキンソン病などが隠れている可能性があるので注意が必要です。
治療は薬が全てでは無いので、食事や運動、生活習慣のについても相談されると良いですね。
根気強く治療に取り組めば、きっと快適な日々が訪れるでしょう。
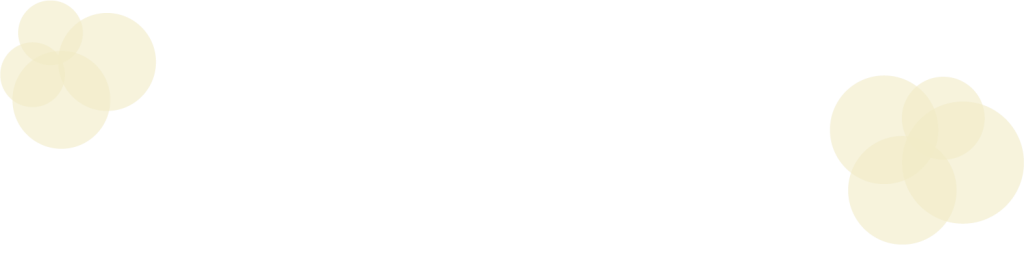
最後に、
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事がお役に立てれば大変幸いです。
以下に刺激性下剤の成分リストを表記して、終わりとさせていただきます。
どうもありがとうございました。

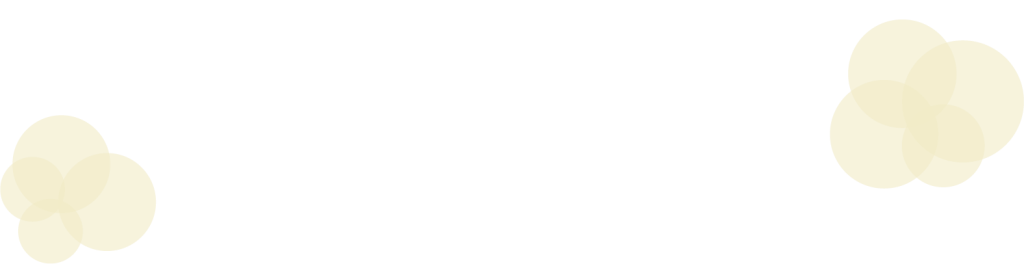
PLUS α !
アドバイス お茶 🍵 について
①『なんとか茶』はくすりより危ない?
実はよく売れている『なんとか茶』の中には、飲み続けると将来的に便秘を悪化させてしまう危ないものがあります。
言い換えれば、「刺激性下剤が入っているもの」と「刺激性下剤が入っていないもの」があります。
便通改善を匂わす言葉の書いてあるお茶には刺激性下剤が入っている割合は高いように思います。
薬機法や景品表示法の関係で露骨には便が出るとは言えないので、
「どっさり」とか「モリモリ」とか「スッキリ」などという表現がよく使われています。
有名な南雲先生監修のあじかんのごぼう茶などの刺激性下剤成分が一切入ってないお茶は全く問題ありません。
刺激性下剤が入っているお茶に関しては、薬と同じで服用方法に注意が必要です。
できれば服用をやめていただきたいところですが、いきなりやめると便秘になりますから注意してください。(前述の通り)
便秘に困っているときに感動のお茶との出会いがあったら、それは飲み続けますよね。
でも、
「くすりじゃないから安全」「お茶だから気軽に何杯でも飲める」
と言って毎日のように嬉しく飲んでいると、耐性が生じ、いよいよ本格的な慢性便秘が完成してしまうのです。
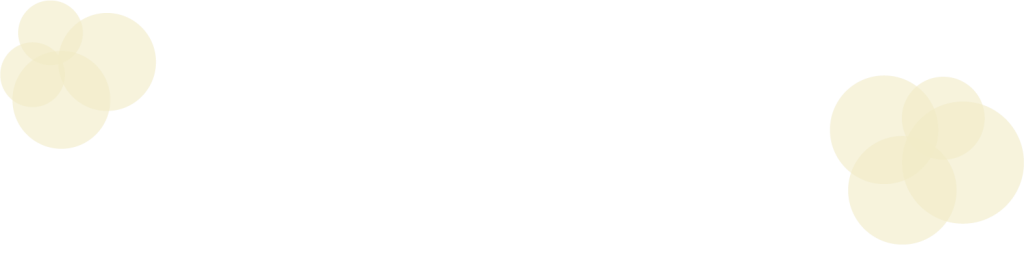
①どうやって安全なものとそうでないものを見分けるのか
見分ける唯一の方法は、
「原材料を全てチェックすること!」
以下に《刺激性下剤の成分リスト》を挙げておきます。
パッケージ裏、あるいは商品サイト等に載っている「原材料」と
以下の《刺激性下剤の成分リスト》を見比べてください。

中でも注意していただきたいのが「アロエ」や「キャンドルブッシュ」です。
「アロエ」って良さそうではありませんか?
実はアロエも刺激性下剤のセンノシドの類似物質が含まれています。
「キャンドルブッシュ」ってなんかおしゃれ感あって、美容や健康に良い感じってしませんか?
ところが、これも医薬品として使用されるセンナの同属植物であり、センノシドを含みます。
なんか良さそうと思って飲んでいると、知らない間に大量のセンノシドを摂取してしまっている可能性があるんです。
「キャンドルブッシュ」という良さげな響とは裏腹に、これはあなたの将来をよくない方向に導いてしまいます。
さらに追加しておきますと、どくだみ茶、あさがお茶、ハブ茶も同様に飲み続けると危険です。
それぞれ、ジョウヤク、ケンゴシ、ケツメイシが入ってます。
まず、市販の便秘薬にしても、健康茶にしても、まず表示をみましょう!
お茶🍵だから大丈夫、漢方だから安心、とは思わないことが重要です。
おまけ
便秘関連の漢方では大建中湯以外は刺激性下剤が入っていると考えた方が無難です。
(桂枝加芍薬湯は便通に関わりますが、刺激性下剤は入ってません。)
授乳中・妊活中の方へ
授乳中の方は刺激性下剤の成分が含まれたものの使用はお控えください。
吸収された成分の 一部が乳汁中に移行し、乳児が下痢をしてしまいます。
ということは、
将来的に子どもが欲しいとお考えの女性の方も、これらを使用しないことが賢明です。
《刺激性下剤の成分リスト》
以下は現在更新中です。
センナ、
センノシド(センナから抽出)
ダイオウ、
カサントラノール、
ビサコジル、
ピコスルファートナトリウム
センナ
キャンドルブッシュ(別名:ゴールデンキャンドル、学名:カッシアアラタ)
大黄
アロエ(センノシド類似物質)
ジュウヤク(ドクダミ科ドクダミの全草)
ケンゴシ(ヒルガオ科アサガオの種子)
ケツメイシ(エビスグサの種子)ハブ茶
大黄を含む漢方薬(大黄甘草湯、大黄牡丹皮湯、麻子仁丸等、他にも多数)
便秘関連の漢方では大建中湯以外は刺激性下剤が入っていると考えた方が無難です。
(桂枝加芍薬湯は便通に関わりますが、刺激性下剤は入ってません。)
キャンドルブッシュを含む健康茶
―下剤成分(センノシド)を含むため過剰摂取に注意―https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140123_1.pdf
おまけ
刺激性下剤をやめた人が口を揃えたように言われることがあります。
「以前のようなスッキリ感が無くなった」というような内容です。
そのスッキリ感は、過剰な感覚である可能性があります。
同じスッキリ感を求めない方が良いです。
数日に一度、腹痛や不快感なく硬さの良い便がそれなりに出ていれば良しとしましょう。


